
|
| |
|
| 導入事例1. |
機器メーカーで社員数も拠点も多い
大手製造業A社の場合 |
ビジネスコンプライアンスを整備して、会社の敷地外にノートPCの持ち出しを基本的に禁止した。
社員数が多いため、それに比例して出先拠点への出張者も多い。そこで管理側では出張者専用パソコンを用意してその利用をサポートしている。
今までは管理方法がマンパワーに頼り過ぎて適切ではなかった上に、出張者専用のパソコン数も上位者の指示で、経費削減の為に台数を減らす事になった。
だが利用者の利便性を犠牲にする事無く、効率良い最適な個数まで管理台数を減らす事は容易ではなく、管理者は困っていた。
また同時に高額備品(プロジェクタ、デジカメなど)もきちんと保管・管理したいと考えている。 |
<現状の問題点・要望> |
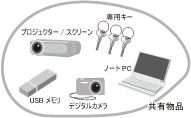
 
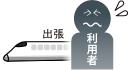 |
 |
出張者は当日使えるパソコンがあるかどうかわからないまま出かけるので不安がある |
 |
管理側は利用ピーク時に合わせたパソコン台数を用意し、出張者の利便性を重視しているが、コストが嵩み問題となっている |
 |
管理側から持ち出し時に管理台帳へ記入するよう指示されているが、以前記載忘れがあり社内トラブルの原因となった |
 |
社内で利用するルールを作ったにもかかわらず、借りたい利用者が管理担当者に頭を下げてお願いしないと備品が借りられないのは不愉快とのトラブルが発生し、社内の雰囲気が悪くなった |
 |
社内にあるその他の備品もキー付きの保管庫に入れているが、持出し管理が不十分で社員より苦情が来たことがあった |
|
 |
| |
<導入後> |
| |
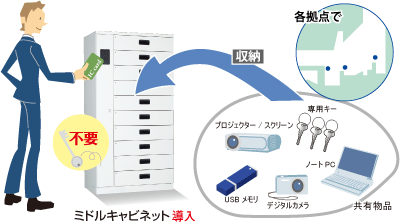 |
 |
「予約管理システム」を導入することで貸し出し時のトラブルが無くなった |
 |
出張者はスケジュールが決まり次第、行き先拠点の貸し出し用ノートPCを予約することで、借りれない心配が無くなった |
 |
管理側は稼動状況を把握しやすくなったことで、必要最小限の備品を最適な状態で配置することが出来た |
 |
記帳忘れが無くなり、利用側も利用状況が「見える化」されることで利用スケジュールが立てやすくなった |
 |
利用側は予約の利用方法が簡単なことから、簡単・自動で備品の借り出しが出来るようになった。また管理側も利用状況をつぶさにチェックできて、貸出しの度に忙しく対応しなくても良くなった。その上、運用が上手く行くようになると貸出し時に発生するトラブルが減少するので、社内の雰囲気が良くなった。 |
 |
備品の利用も「ICカード+予約管理システム」を使うことで、専用キーの持ち出しでのトラブルが無くなり、苦情が減少した |
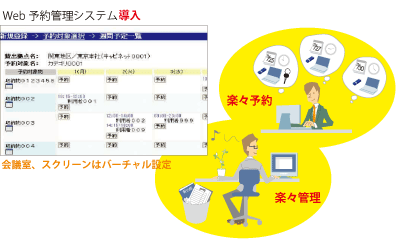 |
|
|
|
| 導入事例2. |
たくさんの検証用ノートPCを利用している
大手製造業B社の場合 |
| 電子回路の評価・試験を行っている企業で、検証用のノートPCが多数利用されている企業。作業テーマ別に試験するので頻繁にノートPCを持ち出すことが多く、技術担当者の利用頻度が高い。当初は都度管理者に借り出しの手続きを行なっていたが、利用頻度が高いため途中より管理者が立ち会わず、利用者が記帳して持ち出す仕組みとした。今のところノートPCの紛失はまだ無いが、紛失事故が起こる前に対策を打ちたいと管理者は考えていた。 |
<現状の問題点・要望> |
 
 
|
 |
利用者は借りる度にまじめに記帳しているが、共用備品であるため、取扱いにはあまり気を使っていない |
 |
管理者は誰がどのくらいの頻度で利用しているか、管理帳を見に行かないと判らない |
 |
管理者は常にノートPCが紛失するのではないかと不安に思っている |
 |
今までのセキュリティ製品は収納個数が少ないため、1台収納あたりのイニシャルコストが高くなる |
|
 |
<導入後> |
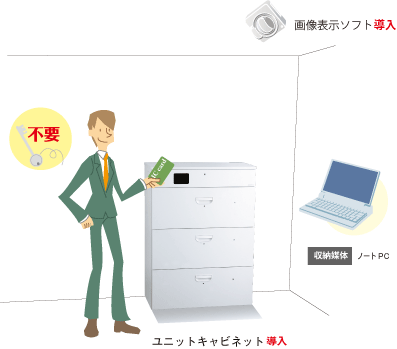 |
 |
利用者はICカードをかざすだけで、記帳する必要が無くなり、利用方法が簡単になった |
 |
管理者は使用ログを見に行く事で、利用頻度を確認できる |
 |
ICカードとIPカメラを連動する事により、利用者のなりすましの防止や持ち出した状態を映像データで残せるので管理側は安心して運用できる |
 |
ユニットキャビネットを利用することでノートPCの収納個数が多くなり、1台収納あたりのイニシャルコストを抑えることが出来た |
 |
|
|
|
| 導入事例3. |
ラック設置本数が1,000本以上ある
データセンターC社の場合 |
| 顧客が厳重保管を要求しているストレージテープについて、今まで耐火金庫に入れていたが、その運用方法に不安があった。センター内ではストレージテープ以外にも保管したい接続ケーブルやノートPCなどもあり、顧客に安心してもらえる独自の保管サービスを構築したいと考えていた。 |
<現状の問題点・要望> |
 |
耐火金庫では持ち出し時や収納時に「誰が」「いつ」作業したのか履歴が取れない為、顧客も不安に思っていた |
 |
備品については保管義務も無いのに顧客の持ち物ということで管理に気を使う |
  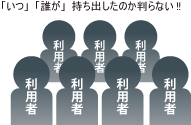 |
|
 |
<導入後> |
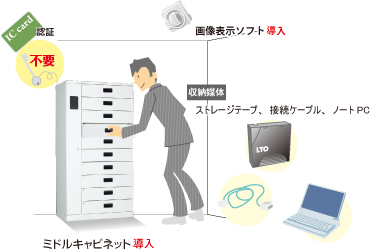 |
 |
ICカードで開閉履歴が確実に記録されるので、「誰が」「いつ」利用したのか後日すぐ確認できる |
 |
顧客から預かった備品を利用履歴が取れるキャビネットに収納したため、利用者がはっきりして預かり責任の重圧から逃れられる |
 |
使用ログのチェックで利用者と
利用時間が特定できる |
|
|
|
|
| 導入事例4. |
メンテナンス業務を請け負っている
メンテナンス業D社の場合 |
| メンテナンス実務の担当者に対して、1人1台の割合でメンテナンス用ノートPCを持たせている。このメンテナンス用ノートPCには顧客情報が満載で、ノートPCを紛失すると大きな問題となる。最近、企業の情報漏洩事件が多発していることから、具体的な対策として安心して運用できる仕組みを検討していた。 |
<現状の問題点・要望> |
 |
持ち出されたメンテナンス用ノートPCの保管方法が曖昧で決まったルールも無く、取り扱いは各人の裁量に任されていた |
 |
他人のノートPCを持ち出せないような、なりすまし対策が出来ていない |
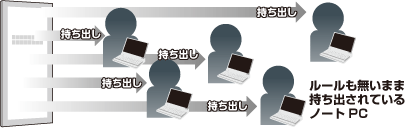 |
|
 |
<導入後> |
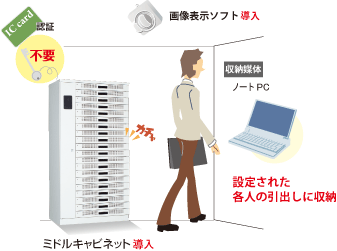 |
 |
各担当者別に保管場所を振り分け、帰社時には必ず専用引出しに収納して帰ることをルール化した |
 |
各担当者の引出しは本人のICカードと管理者のICカードでしか利用できないように指定した。またIPカメラも連携したので、セキュリティレベルが上がってノートPCの保管に関する不安が無くなった。 |
 |
| ・ |
各引出しにAC100V電源を標準装備 |
| ・ |
LANポートの設置も可能
(オプション) |
|
|
|
|
|
| 導入事例5. |
官公庁
Eの場合 |
| 役所で取り扱うメディアの保管用として収納キャビを検討。以前、情報漏洩でこうむる「インシデントに関する調査報告書」のデータを見て、不安に思い具体的に検討を始めた。データを全てメディア化しているが、メディアは外形サイズが小さい上にデータの収納容量も多いので、担当者の心配事も絶えない。 |
<現状の問題点・要望> |
 |
通常のキー付きロッカーでは利用状況を漏れなく把握できない |
 |
通常のキーは又貸しができるため、利用者を確実に特定できない上に、以前収納ロッカーのキーが紛失したことで、メディアの保管・管理体制が脅かされたことがあり、管理側は気が抜けない(安心出来ない) |
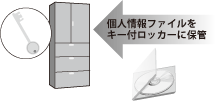  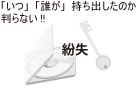 |
|
 |
<導入後> |
 |
 |
「いつ」「誰が」が利用ログで毎回記録されるので、管理側は利用状況を簡単に把握できるようになった。また副産物として、メディアのサイズに合わせた収納キャビを選択したので収納効率が上がり、無駄なく保管・管理できるようになった。 |
 |
ICカードは個人に付与されているため又貸しの心配が無くなり、セキュリティのレベルが上がった。また通常のキーは返却されるまで別の担当者が利用できないが、ICカードはそれ自体が専用キーとなるので、複数人が効率よく利用できて作業効率が上がった。 |
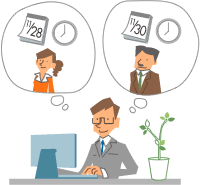 |
使用ログのチェックで
不正を働く職員を牽制 |
|
|
|